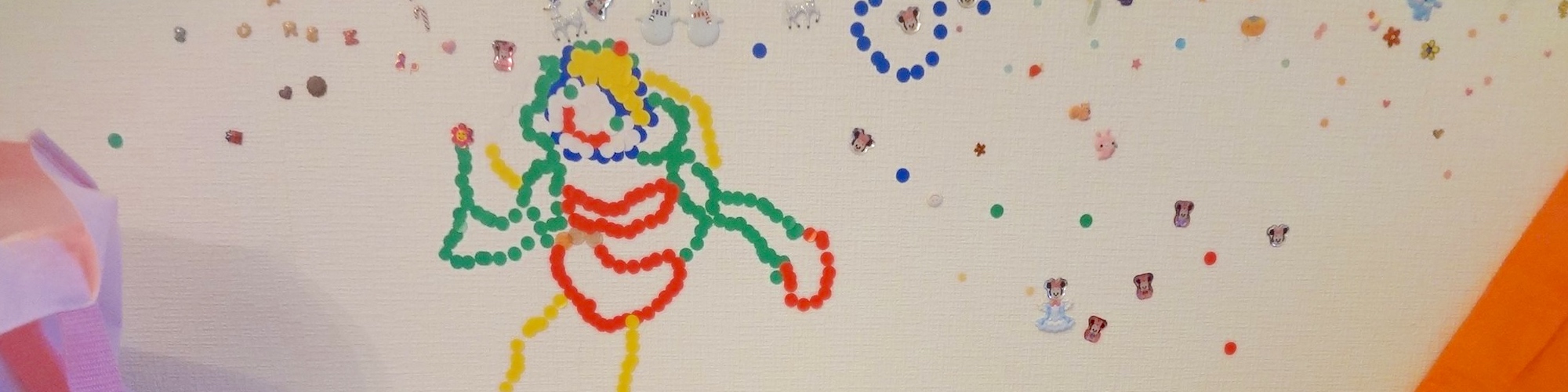季節感を昔ながらの暦から味わってみようと、今年は「節気」に注目しています。
毎年、
11月7日頃から11月21日頃までの時期は、二十四節気の19番目、「立冬」にあたります。
11月22日頃から12月6日頃までの時期は、二十四節気の20番目、「小雪」にあたります。
今回は、この2つをまとめてみました。
立冬ってなに?
二十四節気は太陽暦の1年を24等分したものです。詳しくは立春の項を参照。
立冬は、前述のように二十四節気の19番目、11月7日頃から11月21日頃までの時期です。
一月、二月、といった月を二十四節気から見ると、それぞれの月は、「節気(節)」(二十四節気の奇数番目)と「中気(中)」(偶数番目)から成り立っています。
旧暦の十月の節(奇数番目)に当たるのが、 立冬なんですね。
2020年の立冬は?
2020年は、11月7日(土)に立冬です。
そこから22日に小雪になるまで、15日間続きます。
立冬の意味
日本気象協会の「季節のことば」によると、立冬の定義は「冬の生まれるころ」。
「冬が立つ」からそのままの意味ですが、今の感覚でも、立冬のころ、冬の萌芽はかんじられるものかしら。
新暦の11月は、なかなか秋真っ盛りな印象なので、この時期になってくると、毎年、11月は秋なのか、冬なのか、自問自答します。
自分が子どもの頃の11月は、もう少しは寒かったような気がしますね。
立冬から気をつけたい「冷え」と「乾き」
冬になると、例えば皮膚がカサカサするような渇きと、冷えへの対策が必要だと言われます。
自分は渇いていても、芯まで冷えていると水分を吸収できないことから、渇きの対策と冷えの対策ってセットなんだそうです。
冷えには気をつけて、まださほど寒いと感じなくても、首回りや手首、足首を守ってあげることを始めてください。
腹巻もいいですね♪
同時に、温かい食べ物から水分を取って、温まりつつ乾きをいやすのが、理にかなっています。
鍋物やスープは、実際、美味しくなってきますよね。
まだ秋っぽい現代の立冬でも、このころから根菜たっぷりの煮物だったり、鍋だったりの汁気の多いメニューを増やしていけば、冬の養生にもなるはずです。
小雪ってなに?
小雪は、前述のように、二十四節気の20番目、11月22日頃から12月6日頃頃までの時期です。
旧暦の十月の中(偶数番目)に当たりますね。
2020年の小雪は?
11月22日(日)から小雪です。
そこから12月6日まで、15日間続きます。
小雪の意味
日本気象協会の「季節のことば」によると、小雪の定義は「初雪(はつゆき)」。
現在の11月では北海道で、まだ立冬の頃に初雪がふっています。
が、日本全体としては、なかなか雪にはお目にかかれないですよね!
立冬・小雪のころに食べたいもの
冬に食べたいもの、と考えてもいいかと思います。
五行で考えると、冬は黒です。
黒ゴマ、黒豆、ワカメ、ひじき、昆布など、黒に分類されるものを、上に書いたような温かいものと一緒に、毎日少しずつでも取り入れましょう。
以下の記事では、黒ごまだらけのマグロのたたきの作り方をご紹介しています。
簡単で美味しいです。
西太后は、黒米を毎日食べていたそうですよ。この季節、黒米ごはんもいいのではないでしょうか。
主食は、パンよりは断然ごはんです。水分多く含んでますからね^^
冬は「腎」の養生も
五行でいうところの冬の黒に対応する臓器は「腎」です。
中医学でいう腎は、腎臓だけじゃなくて、「生殖機能」「発育」「老化」に深く関わっています。
どれも見過ごせないキーワードですよね。
子どものおねしょが増えるなどもしかり、冷やすと生理痛がひどくなるとか、わかりやすい対応関係が頭をかすめます。
老化がらみで行くと、朝、起きづらくなるのは、寒いからだけではなくて、早寝、遅起きで、ゆっくり休むくらいのほうが、やっぱり腎にいいんだそうです。
家族全体が、なんとなく、起きづらくなっていたりしませんか?
腎の養生が必要だからかもしれませんよ。
大人は、睡眠時間の確保はなかなか難しいけど、寝過ぎたー!と思うよりは、いっそ開き直って眠るようにしましょう 😉 。
寒い冬にオススメ♪デスクワークついでの足マッサージ
うっかり足を冷やしたときにオススメなのが、足の指の第3指と第4指の間を、すりあげたり、押し広げたりしてみてくださいね。
表からも裏からも同時に押さえるといいそうです。
冷やした!と思うときは私もたまにやってます。
椅子に座りながらもできるので、何かを読みながらちょっと揉むと、漫然と冷えた足を揉むより、効果が高い気がします。
これをやると、ちゃんと足の裏が、三点で、地に着きますよ!
☆ 望月 索 ☆
一般社団法人 日本マクロヘルス協会理事
【参考文献】
「季節のことば」(日本気象協会 編)
|
|
|
|