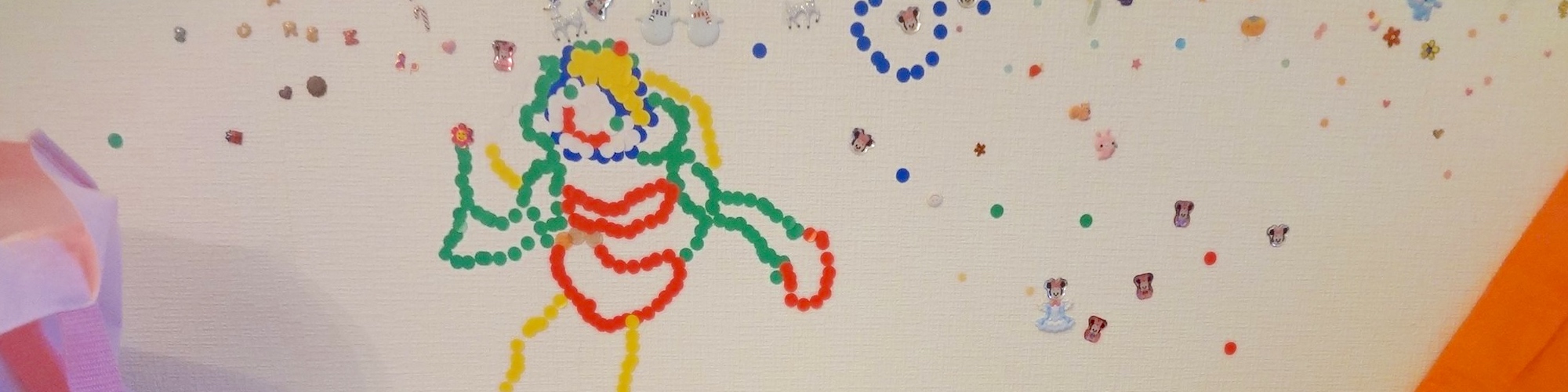下の子は上の子より常に小さいから、気をつけているつもりでも、甘やかしすぎ!と(上の子から)指摘されます……
その結果でしょうか、いちばん下の子がじっさい、いちばん注文が多く、主張が激しいです。
きょうだいげんかに揉まれつつ、思い出したことを書こうと思います。
スタンフォード大の実験による、子ども時代の自制心と将来の成功調査
子どもの自制心を測るために行われた一連の実験があります。
マシュマロテストってご存知ですか?
いろんなバージョンがあり、たぶん一番有名なのが、「子ども時代の自制心と、将来の社会的成果の関連性を調査した」スタンフォード大の実験です。
1970年におこなわれ、1988年、2011年と、追跡調査されているそう。
子どもがどう成長しているか見ていく実験ですものね。追跡していかないとですよね。
マシュマロテストの内容は、下の本『マシュマロ・テスト 成功する子・しない子』にくわしくでています。
|
|
マシュマロテストとは
簡単にご紹介します。
机と椅子しかないような部屋に子どもを通します。
机の上のお皿には、マシュマロが1個のっています。
そのマシュマロを、大人が見ていない状態で、15分間食べるのをガマンできたら、もう1個あげる。と、約束する。
さあ、子どもは食べずにガマンできる?
というプロセスです。もちろん「見てない」と言いつつ大人は隠しカメラで見ています。
結果……
……最後までガマンし通して2個目のマシュマロを手に入れた子どもは、1/3ほどだそうです。
で、以下、Wikipedia からの引用です。
ウォルター・ミシェル【注:研究者の名前です】の娘も実験に参加した一人だったが、娘の成長につれ、ミシェルは実験結果と、児童の成長後の社会的な成功度の間に、当初予期していなかった興味深い相関性があることに気がついた。そして1988年に追跡調査が実施された。その結果は、就学前における自制心の有無は十数年を経た後も持続していること、またマシュマロを食べなかった子どもと食べた子どもをグループにした場合、マシュマロを食べなかったグループが周囲からより優秀と評価されていること、さらに両グループ間では、大学進学適性試験(SAT)の点数には、トータル・スコアで平均210ポイントの相違が認められるというもので あった。ウォルター・ミシェルはこの実験から、幼児期においてはIQより、自制心の強さのほうが将来のSATの点数にはるかに大きく影響すると結論した。2011年にはさらに追跡調査が行われ、この傾向が生涯のずっと後まで継続していることが明らかにされた。
Wikipediaより
就学前に身につけていた自制心が、将来の成功を導く……!
と、まあ、ガマンのできる子どもに育てるにはどうする? というような問題系を導き出すための枕としてよく使われています。
実際、読んでドキッとした人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。
……うちの主張だらけの、可愛い怪獣ちゃんを見ていると、まあとてもじゃないけど、社会的成功は成し遂げられません。
この子、絶対待たずにマシュマロ食べて、そのうえで2個目を、もらえるまで要求するね!!
と、オチをつけてもいいのですが、続きがあります。
テストで問われるのは自制心? 信頼?
この実験、いろんなバージョンがありまして、上記は自制心にひもづけられたもの。
でも、同じ実験を、自制や意志の力よりも、「期待」にひもづけたものもあるんです。
比較的最近になって、過去の経験が行動にどう影響しうるか、を、あわせて調べたマシュマロテストがありました。
マシュマロの話がまったく出ていない段階で、実験に参加した子どもに工作を始めさせます。
実験する大人は、パッとしねーなーと子どもが思うような工作の材料を子どもに渡してですね、もっといい材料を持ってくるよ〜と約束します。
で、子どもたちはひそかに二つのグループに分けられていて、一方のグループでは、大人は約束どおりにもっとよい材料を持って戻ってきます。
もう一方のグループでは、大人は約束を破り、手ぶらで戻ってきて、ただ謝るんです。
その工作のあと、ふつうのマシュマロテストをやるんですね。
その二つのグループで、マシュマロを食べる/食べないに、どのような違いが見られたと思いますか?
ご想像の通り、
材料を持ってきてもらえなかったグループ=大人は信用できない、という経験をしたグループの子どものほうが、実験者が戻ってくる前にマシュマロを食べてしまい、もう一つもらえるチャンスを手放す傾向が強かったそうです。
これは、社会的成功や自制心などと紐づけられた説明より、もっと胸が痛む仮説に気づかせます。
つまり、大人は信頼できないと思わされた、思って育った子どもは、チャンスをつかめない、ということ。
自制を学ぶことは大事だけど、それと社会的成功は必ずしもリンクしないかもしれなくて、信頼できる大人が絶えずそばにいる環境で育つことも、子どもにとっては、間違いなく大切なんですよね。
長く続いている実験というのは、読み解き方そのものでも示唆に富みます。
二度目の実験については『平均思考は捨てなさい』から。
下の記事で紹介しています。
余計な学習をさせないように…
そう思うと、自制は身についてないけど、なにを言っても大丈夫という信頼は、うちの小さな怪獣にもたぶん身についていると思えます。
ひいては、「うるさく主張し続ければ獲得できる」という余計な学習をさせないことが大切。
絶対譲れない線はとにかくゆずらないようにしないといけないな、と思いました。