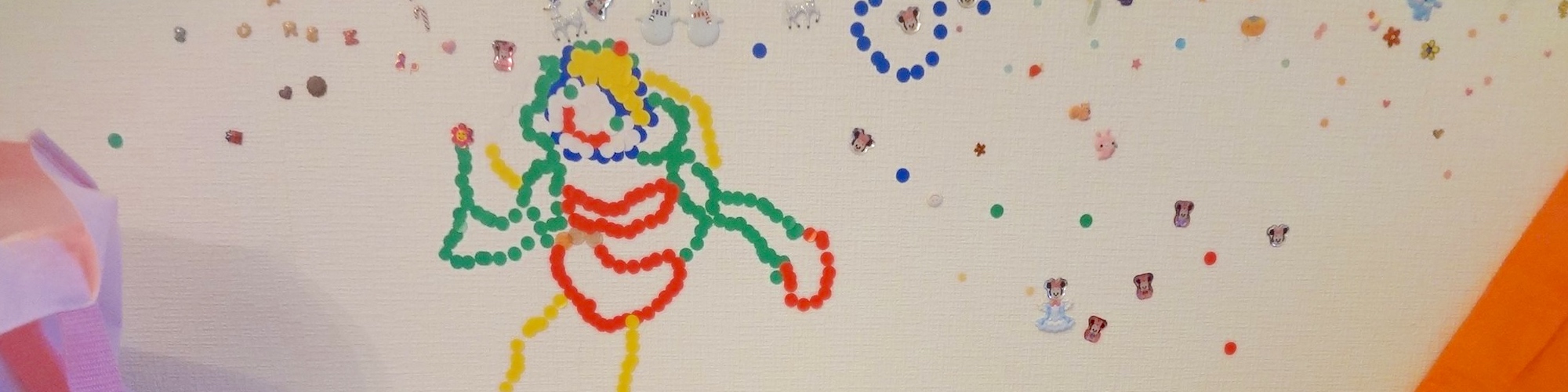下の子が、これまで自分がした悪いことを、家族みんなに知らせてあやまるのを流行らせています。
目がはなせるくらい大きくなってからでも、親が注意したくなることをしているのがよくわかります。
子どもはなんの実験なのか、思わぬことをする、そういう好奇心は自然……。
一方、人見知り、場所見知り、といった言葉があるように、子どもは見慣れないものが苦手です。
新しいものと慣れたもののバランスってどうなっているのか?
人間に共通する、興味深いデータがあります。
「新しいもの」と「これまでで一番いいもの」、成功するのはどちら?
「新しいもの」と「これまでで一番いいもの」の、どちらを選ぶのがいいと思いますか?
子どももそうですが、人は新しいものが好き。一方、慣れ親しんだものも好き。
ここで問題です。
一度も試したものがない「新しい」ものと、10回中7回成功したものだと、どちらを選ぶのがいいと思いますか?
数学的に考えると……
7割の成功率を誇るものより、全く新しいものに賭けるほうが、当たる確率が高くなるんだそうです。
特に、今も未来もほぼ同じであると考えると、全く新しい知らないもの……偶然に賭ける価値はさらに高くなります。
でも、今も未来もほぼ同じなのかといえば、そんなことはないはずですよね。
例えばもうすぐ引っ越すのなら、今の街で新しいお店を選んで食事をするよりは、「美味しい」と知っているなじみのお店にいくほうが、「成功する」可能性は高くなるわけです。
が、ずっとそこに住むのなら、次々新しいものを試していく、探索の段階はあっていい。
その探索には、その後、結果を「活用」していく段階が続くわけだから……。
偶然性にかけるのも、合理的なあり方です。
「新しいもの」から「慣れたもの」へと移行するタイミング
「次々試していく」という時に、どれくらい試せばいいか、という問題設定もあります。
その場合、キーになる数字は、37パーセントなんだそうです。
例えば、引っ越し先の物件を探すとします。
部屋探しに1カ月かけるとしたら、37パーセント……つまり最初の11日間まではただ見て、そこから先は、それまでで一番いい物件を即座に選ぶといいそうです。
そうすることが最良の選び方で、それで成功する確率も37パーセント(選択時も成功時も、どちらも37なんです)。
えっ。つまり失敗が63パーセント!?
とはいえ、何かの目安にはなりますよね。
期間が限られる時に、一番いいものを選びたくて、迷うようなら、37パーセントまではただ見て、そのあと一番いいと思ったものに飛びつけばいいのです。
「後悔先に立たず」も真

……でも、63パーセント失敗すると想定されるもののために、目の前の物件を素通りするのはふつうに迷う。
そこに、「後悔」という変数を入れると、計算結果も変わるそうです。
神様じゃないので、「一番いい選択」なんてできない。
常に後悔はあるから、その総量を減らすというベクトルで考えます。
後悔基準で「一番いいもの」を選んでいると、それ以外の戦略を選んだ場合よりも、後悔が増えるペースも蓄積するペースも遅くなるそうです。
つまり、後悔最小化をめざせば、年を追うごとに、前の年よりも後悔が減る。という数学的事態がありうるわけですね。
何才まで新しいものを追うのが一番いい?
ここで、条件をとても単純化して、人間の人生に当てはめて考えてみると、37パーセントの成功のために、何歳まで探索を続けるか、という問いもあり得ます。
子どものうちは次々新しいものを試す、そのほうが合理的、というのはわかる。
まー小さい子はちっともじっとしてませんし、赤ちゃんはなんでも口に入れますしねぇ!
横で見ている大人は、すでに試したものを活用する段階に入っているので、ハラハラする。
親の探索の知見を生かしてほしいと願いつつ、子どもの「後悔」が最小化されるように、37パーセント以上も許容することになるわけですねー。
じゃあ、いつまで子ども? いつまで探索段階?
人生、80年生きるとすると、37%の成功のために次々試すに値するのは、何歳までかを単純計算します。
29歳6ヶ月。あ、30歳前の妙齢になってしまいます。
Don’t trust over Thirtyってこと?
じゃあ、30以降は、活用ばかりなの? 新規なし? つまんなさそう……
ここで、条件に「後悔最小化」を入れてみると、いろいろ試した結果をもとに、新しいそれが、「どのくらい良いものとなり得るか」に注目することになります。
楽観性による選択、となるわけです。
たとえ失敗してもこれを選ばないと後悔する、と感じ、楽観的に飛び込むことができるのなら、やって失敗するほうが、やらなくて後悔するより、30過ぎてもリスクが少ないかもしれないです。
残り時間を設定し直すと、老人も若者もない
ちなみに、老人のほうが頭が硬いと思われがちですが、残り時間に対し最適化する、という合理的な選択からそれが行われているからであり、残り時間がのびるという条件をつければ、老人も、若者と同様の選択傾向を示すのだそうです。
つまり、寿命があと20年伸びるなら、若者と同じくらい「探索をする」ことを選ぶ、老人が増えるんですって。
『だってだってのおばあさん』ですね!? だって私5歳だもの。という……
いつから老人? 少なくとも還暦過ぎてもまだ老人じゃない……という現代では、大人もバランスよく「探索」を入れていかないと、たぶんツマンナイし、数学的な最適解でもないようです^^
【参考文献】
|
|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1534673f.0fc33b13.15346740.f2706c3f/?me_id=1213310&item_id=19526508&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5387%2F9784150505387.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)